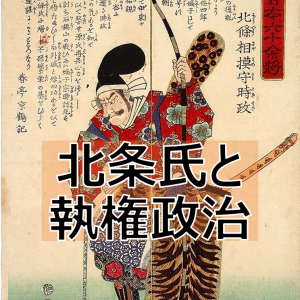蒙古襲来(元寇・文永の役)と北条時宗
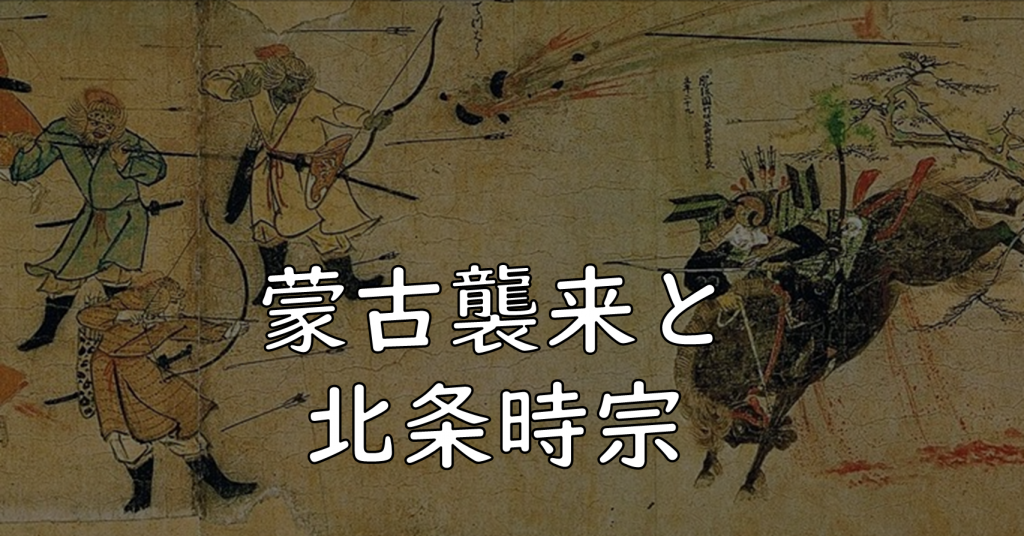
蒙古襲来というと、モンゴル人が大挙して襲来して、日本人を殺しまくった恐るべき戦争というイメージがあります。
当時の執権・北条時宗軍は敗戦間違いなしという戦況でしたが、台風襲来という「神風」が吹いたため、モンゴル軍は退去せざるをえなくなりからくも日本は助かった、というイメージもあります。
高校教科書には、蒙古襲来について下記のように記載されています。
フビライ・ハンは対馬・壱岐を攻め、大挙して九州北部の博多湾に上陸、幕府は九州地方に所領をもつ御家人を動員してこれを迎え撃ったが、元軍の集団戦やすぐれた兵器に対し、一騎打ち戦を主とする日本軍は苦戦におちいった。しかし元軍も損害が大きく、内部の対立などもあって退却した。(文永の役)
山川出版社『詳説 日本史B』
その後、ふたたび元が、日本の征服をめざし、約14万人の大軍をもって九州北部に迫ったが、博多湾岸への上陸をはばまれているあいだに暴風雨がおこって大損害を受け、ふたたび敗退した。(弘安の役)
蒙古襲来、本当はどのような戦いだったのでしょうか?
関連記事:北条氏と執権政治
関連記事:鎌倉殿の13人と承久の乱
関連記事:清和源氏 武士の台頭
元寇・文永の役
フビライ・ハン(クビライ・カアン)
まずは、蒙古襲来を行った張本人、フビライ・ハン(クビライ・カアン)についてです。
10世紀から存在する高麗は、モンゴルによる侵略が1231年から始まり、1259年、高麗はモンゴルに降伏しました。
元々、モンゴルは草原や砂漠に住む騎馬民族を母体とし、騎兵を中心とする戦法が得意であり、東アジアの水田や山地に囲まれた地形への侵攻には手こずりました。
したがって、東アジアではなく西アジアへの侵攻を優先して行いました。
モンゴル人は、もともと遊牧民なので農耕社会というものを知らず、土地が手に入ればよい牧草地ができる、という程度の考えしかなく、農耕社会のような人に田畑を耕させれば食料が自動的に手に入るという仕組みを知りませんでした。
1260年、チンギス・ハンの孫でモンゴルの第5代皇帝に即位したフビライ・ハン(クビライ・カアン)は、最大の敵・南宋を討伐するべく東アジア全体の征服を計画します。
そのため、フビライ・ハンは、これまでの高麗への武力による抑圧策を懐柔策へと方針を変更することになります。

しかし、モンゴル(元)は、日本への2度の侵攻(元寇・蒙古襲来)をはじめ、樺太アイヌ侵攻、ベトナム侵攻、ジャワ侵攻などでは、現地勢力の激しい抵抗を受け敗退しています。
これらはすべて大陸のような草原・砂漠ではなく、水田・山地で成り立つ地域であり、モンゴル軍お得意の騎兵戦が功を奏しなかった証拠です。
マルコ・ポーロが1271年から1295年にわたりアジア諸国で見聞した内容を口述筆記された旅行記が『東方見聞録』です。
マルコ・ポーロの『東方見聞録』
マルコ・ポーロは、1271年に出発し、1295年に帰国するまでにアジア諸国で見聞した内容を『東方見聞録』として残しています。
1271年というのは日本でいうと文永八年ですから、モンゴルが日本へ使節を派遣してきた時期にあたります。
マルコ・ポーロは、1275年、フビライ・ハン(クビライ・カアン)に謁見します。
1275年は日本では文永十二年ですから文永の役の1年後にあたります。
東方見聞録によると、「ジパングは、マンジ(中国中南部)の東方1500マイルの島国で、莫大な金を産出し、宮殿や民家の屋根は黄金でできているなど、財宝に溢れている。また、ジパングに住むものは、偶像崇拝者で、色が白く外見がよい。また、礼儀正しく穏やかである。葬儀は火葬か土葬であり、火葬の場合は死者の口の中に真珠を含ませる習慣がある。」と書かれています。
いわゆる「黄金の国ジパング」伝説です。
そして、マルコ・ポーロはフビライ・ハンが黄金の国ジパングのこの財宝を入手する計画を立て、軍勢を送るが嵐に会い失敗した、と話したことが書かれています。
黄金で溢れているというのは脚色がすぎるようですが、フビライ・ハンには日本の財宝を入手する意図があったことがうかがえます。
執権・北条時宗

北条時宗は、建長三年(1251年)、鎌倉幕府の執権を世襲する北条氏の得宗家に生まれました。
文永五年(1268年)正月、高麗の使節が元の国書を携えて太宰府に来訪する中、時宗は18歳で第8代執権となります。
まさにモンゴルによる日本侵攻の圧力が高まりつつある中での時宗、執権就任でした。
文永九年(1272年)、六波羅探題の南方の別当で、時宗が執権になった事に不満を持つ異母兄の時輔や、北条時章・教時兄弟を誅殺します。
更に、文永十一年(1274年)、『立正安国論』を幕府に上呈した日蓮を佐渡に配流するなど、国内の引き締めに手を焼いています。
モンゴル・高麗使節団
文永三年(1266年)、第一回の使節が派遣されます。
11月25日、日本宛の国書である「大蒙古国皇帝奉書」を携え、モンゴル国・正使で兵部侍郎・黒的と副使で礼部侍郎・殷弘ら使節団が高麗に到着します。
モンゴル使節団は、高麗人に日本を案内させる予定でした。
黒的ら使節団は、高麗国王・元宗に日本との仲介を命じ、高麗人の枢密院副使・宋君斐と侍御史・金賛らが案内役に任ぜられ、モンゴルの黒的と殷弘を伴い日本に向けて出発しました。
そのため、翌年、宋君斐ら高麗人は、モンゴルの黒的らを朝鮮半島東南岸の巨済島の松辺浦まで案内すると、対馬を臨み、海の荒れ方を見せて、使命を果たす自信を失ったといい、高麗の官吏と共にクビライの下に帰国しました。
この行動に当然、フビライ・ハンは怒り再度、黒的と殷弘を高麗に送り詔を伝え、モンゴルからの詔書と高麗からの詔書を携えて、翌年文永五年(1268年)正月、高麗からの使者・潘阜が日本の太宰府に到着しました。
これに対し日本は鎌倉幕府の時宗に国書が届けられ、最終的には朝廷が「返牒あるべからず」として、回答しないことになりました。
第二回の使者は文永六年(1269年)2月、クビライは再び黒的と殷弘ら使節団を日本へ派遣します。
高麗人・潘阜らの案内で総勢七十数名の使節団が対馬に上陸しました。
使節団は日本から拒まれたため対馬から先には進めず、日本側と押し問答となり対馬島人の塔二郎と弥二郎2名を捕らえて帰国します。
この日本人二人を連れ帰ったことをフビライ・ハンは喜び、多くの宝物を下賜し、フビライの住む燕京の宮殿を観覧させるなど歓待します。
7月、高麗使節は、この島民を連れてモンゴルの国書を携え再び対馬を訪れます。
朝廷は返書を出すことになり、文書博士・菅原長成が返書「太政官牒案」草案を用意しますが、幕府の反対にあって取り止めになりました。
文永八年(1271年)9月、元使である女真人の趙良弼らがモンゴルへの服属を命じる国書を携えて100人余りを引き連れて来ます。
フビライは、趙良弼らが帰還するまでとして、日本に近い高麗の金州に忽林赤、王国昌、洪茶丘のモンゴル軍勢を集結させます。
その後、博多湾の今津に上陸した趙良弼は、日本に滞在していた南宋人と三別抄から妨害を受けながらも博多の守護所に到着しました。
日本は大宰府以東への訪問を拒否、趙良弼はやむなく国書の写しを手渡し、期限を過ぎた場合は武力行使も辞さないとしました。
これに対して朝廷は評定を行いますが、結局これにも返書は与えないことになりました。
さて、これらモンゴルの使節来日に対し、幕府はどのように対応したのでしょう。
記録に残るところでは、北条時宗は、文永九年(1272年)、異国警固番役を設置、九州の御家人に筑前、肥前など北九州沿岸の警固にあたらせました。
しかし、警固番役以外には大軍を九州に行かせたり、防塁を築いたりした形跡はなく、モンゴルを悪霊にみなした神仏祈願に頼ることくらいしかしていません。
蒙古襲来・文永の役
文永十一年(1274年)10月5日、対馬の佐須浦に蒙古軍が接岸し戦闘が始まりました。
日本側は対馬守護少弐景資の代官・宗助国が蒙古軍と対戦しますが、圧倒的な軍勢の前に敗退しました。

元軍が対馬を制覇し次に壱岐島に現れたのが10日後のことでした。
壱岐に続き松浦半島の島々を制覇され、元軍は九州博多湾に侵入してきました。
日本軍の戦法は古来伝統の一騎打ち、つまり一騎づつ名乗り出て相手側も一騎が名乗り出てから戦いますが、蒙古軍は一騎打ちなど取らず、集団で大勢で敵を囲んで捕捉するやり方ですので、日本ははじめから不利な戦いでした。
また、兵器においても「鉄砲(てつはう)」と呼ばれる爆弾や毒矢を使いますので、殺傷能力に差があります。
もっとも違ったのが、上記『蒙古襲来絵詞』に見られるように、軽装の歩兵による集団戦法対日本の騎馬でした。
これが教科書にも見られる”集団戦や優れた武器”による日本苦戦の原因でした。
世界を戦争で侵略してきたモンゴルと、外敵の脅威に対応した経験の無い日本との差は歴然でした。
しかし、元軍は夜になると戦闘を止め軍船は引き上げます。
夜中に暴風雨が到来します。
この暴風雨が来たため元軍は溺れ死ぬものが多数にのぼり撤退した、という説が有力でしたが、暴風雨で撤退させるほどの死者が出るとは思えません。
そこで新たな説として、元軍は偵察を兼ねた侵攻にすぎず、日本征服をするつもりはなく、撤退する予定だったという考えが出てきました。
撤退理由は不明ですが、暴風雨がきっかけとなり日本は侵略されずに済んだことになります。
本当に暴風雨が来たかは不明ですが、この時期(旧暦10月20日は晩秋)に台風が来ることは考えにくく、モンゴルが言い訳として暴風雨と誇張したとも考えられます。
また、日本としては神風によって勝利したということで、神の御加護があったことを喧伝した結果でもあります。
軍備面では、高麗軍の軍船というものが急ごしらえのものであった可能性もあり、冬の嵐で壊滅的打撃を被ったのも一因でした。